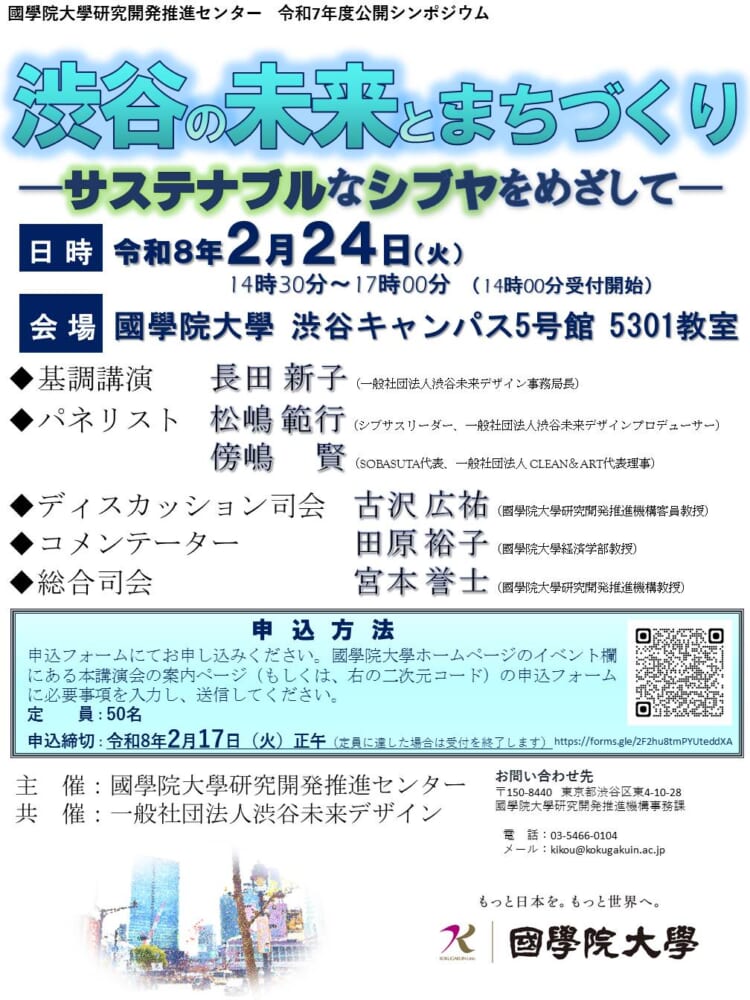明治の政治史は無味乾燥? とんでもない。実際は、こんなにも人間臭く、生々しく、面白い。政治的な混沌から近代国家を生み出そうと政治家や官僚たちが格闘する複雑な動き、そしてその競合と葛藤の中から形作られる新たな政治構造、サントリー学芸賞(思想・歴史)を受賞した坂本一登著『伊藤博文と明治国家形成―「宮中」の制度化と立憲制の導入』(吉川弘文館、1991年→のちに講談社学術文庫、2012年)をはじめとする著作において、そんなドラマを魅力的な文体で描き出してきたのが、坂本一登・法学部教授だ。
歴史をめぐる巨視的な議論と、迷いつつ歩みを進めてきた自身の人生を、あわせて訊ねたインタビュー前編を経て、今回の後編では研究内容にグッと踏み込む。歴史好きの人はもちろん、かつて歴史の授業が肌に合わなかった人も、ぜひ読んでみてほしい。
私は政治史の研究者ですので、当然、専門家の方々と一緒に研究しているわけです。ただ、ものを書くときは、なるだけ専門家だけではなく、一般の読書好きのひとにも興味をもってもらえるように書ければいいなあと思ってやってきました。専門家ではない、門外漢のひとにも、啓発的とまではいえないにしても、できれば歴史は面白いと思ってもらえるような、そんなリーダブルな物語や人間ドラマを書きたいと思ってきました。おそらくそれは、大学院時代に、歴史は物語であり、面白くなければならないという独断と偏見を、ひどく刷り込まれたせいだと思います。もっともそれは、呪いの言葉でもあって、何事もそうですが、言うは易く行うのは難しいので、低い生産性にいつも悩んでいます。ですから、ほんのたまにですが、リップサービスで歴史って興味深いですねとおっしゃってくださる読者に出会うと、我を忘れます(笑)。さて、「長い前置き」はこのくらいにして、研究の内容に移りたいと思います。

坂本一登著『伊藤博文と明治国家形成―「宮中」の制度化と立憲制の導入』(吉川弘文館、1991年→のちに講談社学術文庫、2012年)という本は、当時はあまり評価の高くなかった伊藤博文を中心に、伊藤を再評価しながら明治国家の形成史を描いたものです。が、同時に、もうひとりの主人公として、明治天皇を登場させて叙述したところが、当時としては多少目新しい点だったかと思います。天皇制という言葉は、批判的なニュアンスをこめて、それこそ枕詞のように使用されていましたが、不思議なことに明治天皇が政治史のなかで存在感をもって描かれることは、資料上の問題もあって、ほとんどなかったのです。
制度上の存在ではなく、明治国家形成史の重要なアクターの1人として、生身の人間としての明治天皇を組み込んで政治史を描くということですね。明治天皇は、維新の際、17歳の少年でした。錯綜した政治情勢に翻弄され、当惑しながら複雑な気持ちをいだいて即位したと思います。それゆえ、明治政府との関係も、当初は必ずしも順調だったわけではなく、言葉を選ばずにいえば、ときには駄々をこねて、政府関係者の嘆息の対象になった時期もありました。
実際、国家形成が本格化する明治10年代後半には、何度も政府関係者と天皇との間に衝突が生じています。外務卿が外国交際を推進するため外国要人との面談を天皇に要請しても拒否されたり、海軍の重要なイベントに天皇の出席をお願いしても「炎暑」を理由に拒絶されたり。その背景には、外国嫌い・外出嫌いの天皇と強引にことを進めようとする政府関係者との間のコミュニケーション不足に由来する相互不信がありました。
明治国家の形成というのは、外国の憲法や制度を学習していかに日本に導入するかという問題だけでなく、君主である明治天皇と政府との間にいかに信頼関係を生み出していくかという問題も重要だったのです。そして天皇との信頼関係を成り立たせる上で、伊藤の果たした役割は大きかったと思います。また一旦伊藤を仲介に相互信頼が生まれると、やんちゃだった明治天皇も人が変わったように人間としても立憲君主としても成長していきます。明治天皇の君主としての成長と、明治という時代の成長が、同時代を生きたひとびとには、ひとつに重なり合い、分かちがたいもののように感じられたのかもしれません。だからこそ、明治天皇の死は一人の君主の死以上の喪失感をもたらしたのではないでしょうか。
明治国家形成に関して、もう一つ長い間取り組んできた問題に、明治憲法の制定があります。これについても話せば長くなるので、ここでは、伊藤博文の名前で公刊された『憲法義解』(岩波文庫版・2019年)の解説のさわりだけを紹介しておきます。
「明治憲法は、かつて不磨の大典と呼ばれた。その語感は、憲法が確乎として統一された構想の下に制定されたことを連想させる。また、人によっては、統一された構想ということから、明治十四年政変でプロイセン型立憲政体の採用が決定され、ドイツモデルに基づいて粛々と憲法が制定されたイメージを想起するかもしれない。しかし、明治憲法の制定過程は、決してそのような単純なものでも、予定調和的なものでもなかった。
非西欧世界で初めて本格的に立憲政治を導入するにあたって、憲法をいかに制定すれば、安定と成果を得られるかという問いは、誰にとっても見透しがたく答えるのがむずかしい問題であった。そして、そうした不確実性に対応して、当時の藩閥政府内には、憲法や立憲政治について様々な考え方や構想が存在し、それらの間の相克を反映して、憲法条文と条文の「説明」を確定する作業は、思いのほか紆余曲折をたどったのである」

伊藤博文著『憲法義解』(岩波文庫版・2019年)のほんとうの著者は、伊藤ではなくて、井上毅です。そして、明治憲法の原案をつくり、制定作業を主導していったのも、井上毅でした。その井上毅が憲法草案を作成する過程で、調査したり、推敲したり、議論したりした、貴重な原資料が、実は國學院大學の図書館に寄贈されています。一般的には明治憲法は、今でもあまりよい憲法ではないという印象をおもちの方が多いのかもしれません。しかし、それらの資料をみていると、おそらく歴史の法廷に立たされることを自覚していた、一般に憲法制定者たちと呼ばれる井上や伊藤および伊東巳代治、金子堅太郎らが、歴史への弁明を試みるかのように、文明的な憲法をめざして、彼らなりにいかに悩み、苦しみ、対立したか、それらの奮闘の軌跡が墨痕の間から浮かび上がってくるような気がします。
近年は、多少時期をずらして、明治憲法体制のゆくえといった漠然としたテーマで、明治憲法体制がどのように展開し、変容していくのかを研究しています。以前に比べれば、人物よりも構造の方に関心の比重が移っているかもしれません。昨年、「第1次西園寺内閣と政友会―「与党システム」の誕生と議会審議の政治資源化」という論文を書いてみました。日本近代史の政党研究にはぶ厚い蓄積がありますが、意外と帝国議会と政治との関係を直接あつかったものは多くなかったからです。現代にまでつながる日本の議会運営の特色は、内閣と政党と議会との間の独特の関係にあるのではないかというのがその見通しですが、まだ試行錯誤の段階にすぎません。本格的に大衆社会が到来したとき、帝国議会がどのように対応した(あるいはしなかった)のかという問題にも興味があります。
資料にもとづいて新しい歴史的事実を発見することをファクト・ファンディングといいます。歴史はファクト・ファンディングに始まりファクト・ファンディングに終わるともいわれます。問題は、そのファクト・ファンディングに、どのような意味があるかということでしょう。資料を読めば自動的に新しい歴史的事実が発見されるわけではなく、ファクト・ファンディングの前には、必ず問いがあります。ですから意味あるファクト・ファンディングを行うということは、意味のある問いを立てることができるかどうかにかかっています。どうすれば意味のある問いを立てられるのか、どんな問いに意味があるのか、難しい問題ですが、われわれはどこから来てどこへ行くのか、それらを探るべく、研究を続けていきたいと思います。
<<前編は「近代国家が形作られていった日本の近代史を探求する理由」
| 1 | 2 |
坂本 一登
研究分野
日本政治史
論文
第1次西園寺内閣と政友会ー「与党システム」の誕生と議会審議の政治資源化(2023/03/31)
明治国家と財政制度ー大蔵省の予算査定権を中心に(2015/03/10)