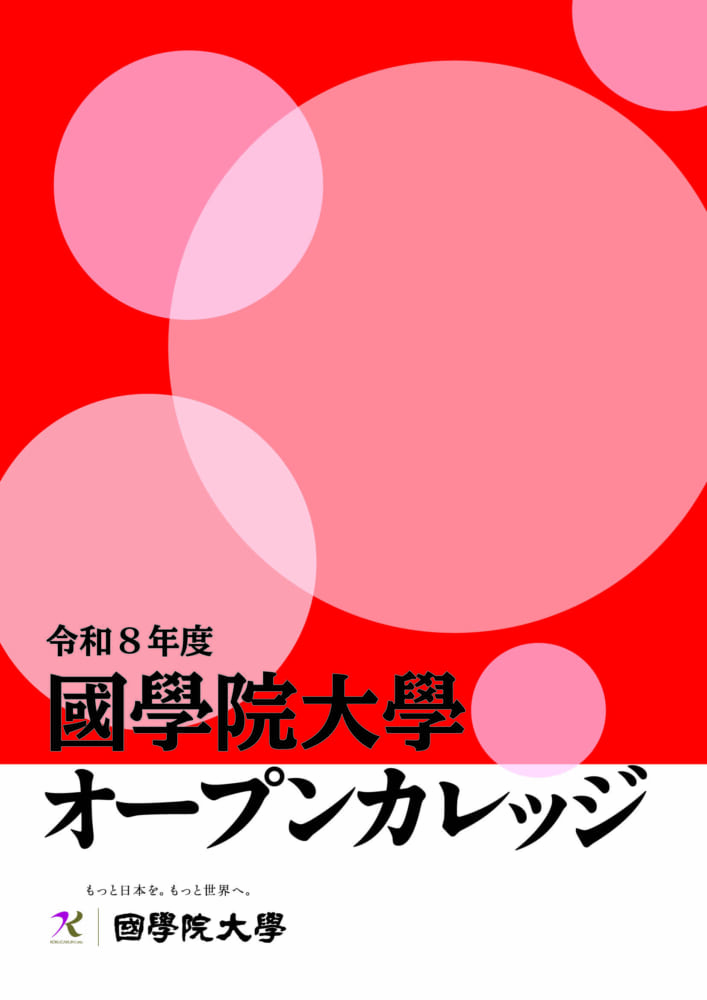幼稚園や保育園で遊びを通して学んでいた子どもたちが、小学校に入ると、整然と教室の席に座り、教科書を順番通りに学んでいくようになる――ごく当たり前の光景、そしてごく一般的な子どもの成長のプロセスのように思われる。
しかし、それは本当に“当たり前”のことなのだろうか。子どもたちは、実は大きなギャップを経験し、時に乗り越えることに困難を感じているのではないのか? そう問うているのが、吉永安里・人間開発学部准教授だ。
自身も幼稚園・小学校それぞれの教育現場で指導にあたり、実践的な知見を深めてきた。子どもたちが幼稚園と小学校のギャップにつまづくことなく、学ぶことは楽しいと感じて生きていけるようになるために。インタビュー前編では、「幼小接続」がなぜ今強調されているのか、その教育的意義と彼女が目指す教育の理想について尋ねた。
幼稚園と小学校の間に横たわる学校文化のギャップ――これが、私のひとつの関心事になっています。
学びに関する指導の場面でいえば、幼稚園では、子どもたちが秋の自然に興味を持ったのなら、葉っぱや木の実などの自然物を収集して造形活動や身体表現に発展させたり、その表現を通して教師や友達と気持ちを通わせたりするなど、――幼稚園指導要領においては「領域」と呼ばれる――「健康」「人間関係」「環境」「言葉」「表現」の5つの領域のねらいを総合的に達成するようにしていきます。
一方で小学校に上がると、1年生の子どもたちは「教科」指導の文化に参入することになります。教科書を開いて、この教材を勉強します、と子どもの興味関心とは関係なく、ねらいや学習方法が先生によって提示されることもあります。もちろん今は、主体的・対話的で深い学び、いわゆるアクティブラーニングが求められる時代ですから先生方も様々な工夫をしていらっしゃいますが、基本的には先生によって計画された単元計画に沿って、子ども自ら目的意識や自覚をもって学習することが求められる学校文化に切り替わるのです。

この間のギャップは、本当に大きい。さすがに最近は「幼小接続」のこともだいぶ知られてきましたのでそんなことはないでしょうが、かつては小学校の先生が幼稚園を参観すると、「いつ始まるんですか?」という質問が出た、などという話も聞きます。つまり、先生も子どもたちも、小学校の先生方からすると区切りもなくずっと遊んでいるようにしか見えない、ということなんです。しかし、小学校の先生にはただの遊びにしか見えなくても、実際はその遊びこそが子どもにとっての全人的な学びであり、総合的な教育の方法なのです。
こうした幼児教育と小学校教育のギャップをどう埋めて、新たな出会いをつくっていくのか――「幼小接続」は、これまでにも段階を踏みながら試みられてきました。今はその第3期に入ったと考えています。
まず第1期は、小学校1年生の児童が、集団行動がとれない、授業を静かに聞いていられずに勝手に歩き回り、教室から出ていってしまうなどの「小1プロブレム」が指摘され始めた頃です。それまで、幼稚園から小学校への移行は大人にとっては、子どもたちが自然に適応していくものという認識があったものが、社会問題として取り上げられるようになって、教育現場がそこにある大きなギャップを自覚し、対応せざるを得なくなった、という時期でした。この頃から、小学校入学前後で、幼稚園・保育所での子ども達の様子を小学校教員に申し送りする情報交換会や、小学校教員と保育者が互いのことを知るために、一緒に自治体の研修を受けたり、授業・保育を互いに参観し合ったりするなどの取り組みが少しずつ始まってきました。また、入学前の園児が小学校に行って、小学生と一緒に遊んだり、校内を案内してもらったり、給食を食べたりするなど幼保小の交流活動も行われるようになってきました。
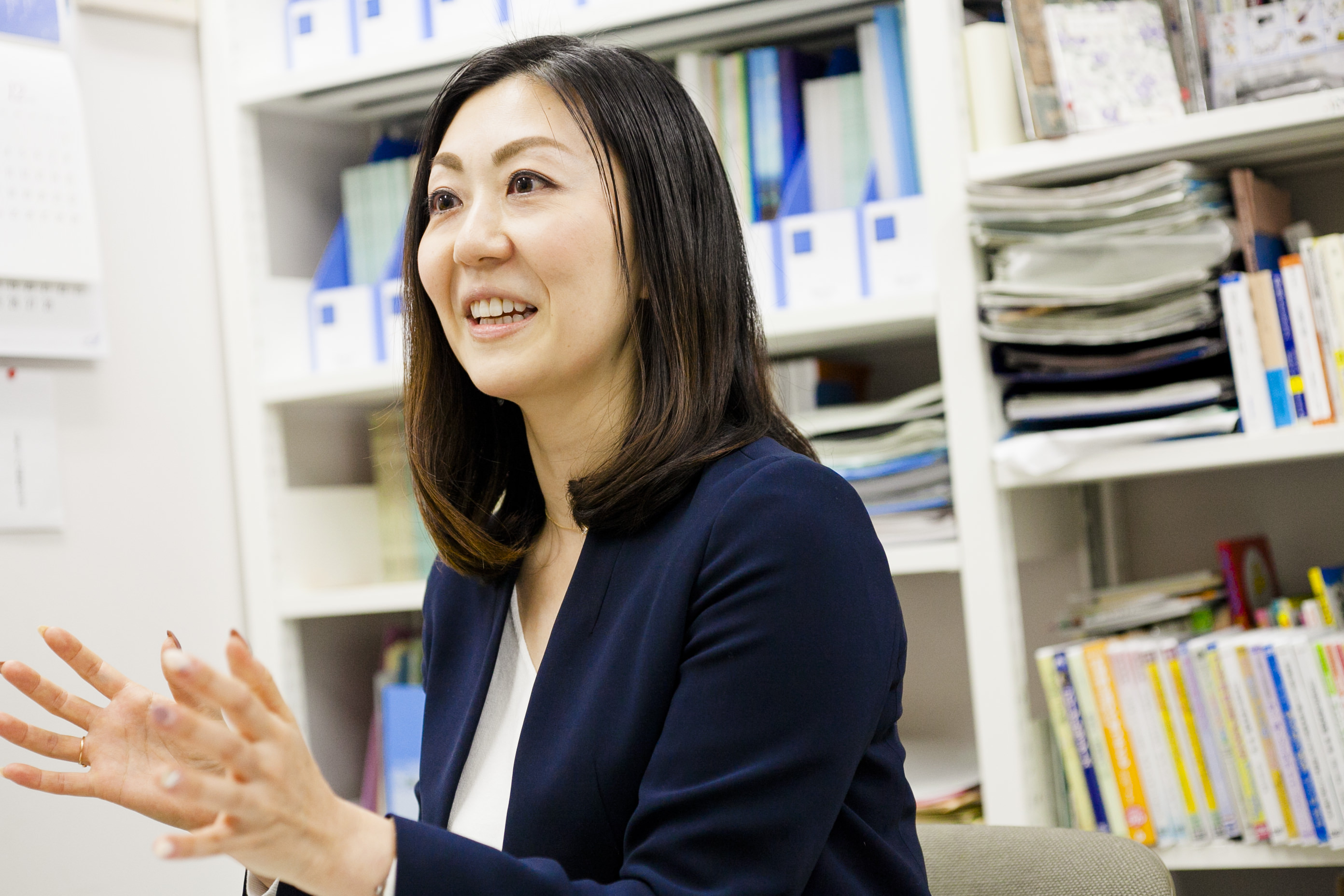
第2期は、そうした幼保小の交流が少しずつ進んできて、各地の小学校で、子どもたちが安心して入学後の生活ができるように、という配慮がなされるようになってきました。ただ、小学校の和式便所の使い方に慣れる、授業を受ける姿勢を厳格に指導する、あるいは幼稚園や保育園で、年長組の子どもたちが小学校のような一人ずつに割り当てられた机に座って活動する、平仮名や計算のお勉強の時間を取るといった小学校文化や生活、学習に子どもをいかに適応させるかという指導が「幼小接続」の取り組みだという誤解も出てきてしまったことは残念なことです。
今は第3期。具体的に、カリキュラムの上で「幼小接続」を達成しようとしている時期です。平成29年に改訂された新「学習指導要領」、「幼稚園教育要領」、「保育所保育方針」、「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」といったものには、すべてこのカリキュラム面での「幼小接続」の視点が含まれています。
私自身、こうした変遷と歩みを同じくするようにして、幼稚園に、そして小学校に勤めてきました。そして小学校教員時代に大学院で研究を始めるにあたって、何が一番の関心事だろうと思ったとき、小学校に上がった子どもたちが、「学ぶことが楽しい」「学校にくるのが楽しい」と思ってくれたら、ということが真っ先に思い浮かんだのです。

もちろん、学校以外の場にも教育の場はありますし、子どもたちが楽しく生きる場はあります。でも、その時の私は小学校の教員でしたから、その枠組みの中で子どもたちが幸せに生活し伸びやかに自己を発揮して学ぶにはどうしたらよいかを考えたかった。そこで研究の対象を「幼小接続」にしたのです。
さらに私の専門は国語教育ですので、幼児期のことばの育ちを小学校の国語の学習にどう活かしつないでいくかを考えたいと思いました。幼児教育と小学校での言葉の指導を、子どもの力を最大限引き出すことができるのか、――実践的な研究の内容は、後編でお伝えできればと思います。
吉永 安里
研究分野
幼児期のことばの発達、小学校国語科教育
論文
人との関係をつなぐ絵本(2024/02/10)
「どうして?」「やってみたい!」があふれる幼児期の学び(2021/11/10)