カリキュラム
2025年6月10日更新
哲学・倫理学コース
古代ギリシア以来、批判的に吟味されつつ継承・展開されてきた哲学の精神を、現代に生きる者として、どのように批判し、理解し、そして受容するかをまず学びます。
哲学概論、哲学史というもっとも基本的な学説の講義をはじめとして、倫理学、論理学、宗教哲学、科学哲学、言語論、インド思想史、日本思想史、そして現代哲学など、多岐にわたる哲学的知識を探るとともに、特殊講義においては具体的なテーマ、あるいは哲学者・思想家に焦点を絞りながら問題を掘り下げます。
ギリシア語、ラテン語、サンスクリット語といった古典語(初級・中級)の授業が開講されているのも大きな特色です。
また自発的・創造的な知的訓練の場として、基礎演習、演習の授業が置かれています。それらは学生各自の哲学的思索を真理へといざなうものであり、その集大成が卒業論文です。
美学・芸術学コース
美学は、西洋哲学の一分科として成立しましたが、諸芸術の動向の理論的・史的考察との関連において独自の展開を見てきました。この美学と、具体的な諸芸術ジャンルの理論的考察としての芸術学、史的・実証的研究としての美術史とを視野に収めるためのコースです。
しかし、美学・芸術学コースだからといって、芸術作品だけが研究対象というわけではありません。目に見えるすべての現象を対象として、ものを考える力と想像力を育成します。
基礎的科目のほか、特殊講義では西洋美術史、日本美術史、東洋美術史、音楽史、映像論、舞踊論、建築論などさまざまな芸術ジャンルについて学びます。演習は純粋に美学理論的なものから個別芸術学的なものまで、特定のテーマを徹底的に掘り下げ、卒業論文に役立ててゆきます。
なお、さらに勉学を進めたい学生のために、大学院文学研究科史学専攻のなかに美学・美術史コースが置かれています。
授業紹介
基礎演習ⅠA
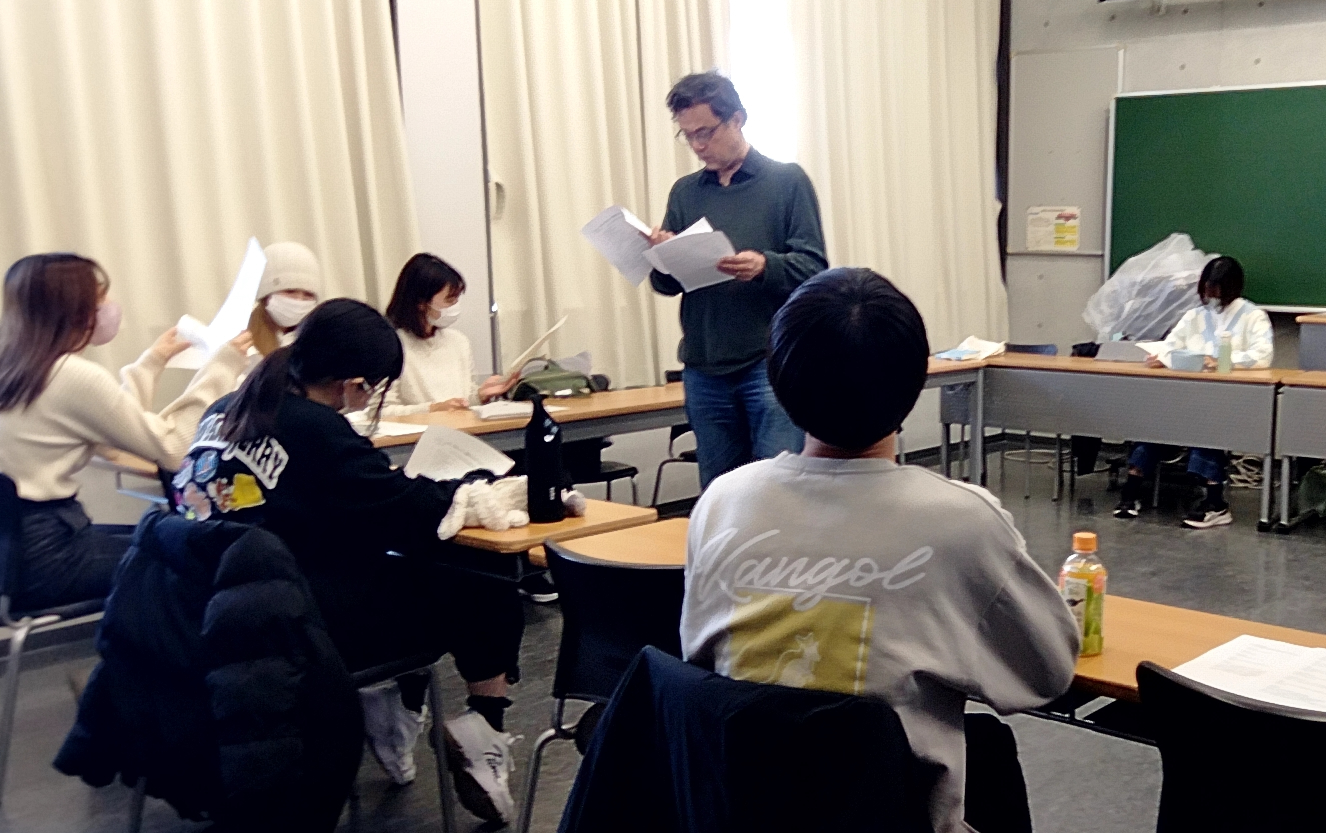
基礎演習ⅠAの授業風景
基礎演習Ⅰ A
担当教員:藤野 寛
哲学の勉強の仕方について哲学的に考えることを試みます。「私はなぜ哲学科の教員/学生になったのか」「大学での勉強は高校までの勉強とどう違うのか」「本・論文をどう読むか」「論文とは日記や小説とは違うどんな文章か」「哲学的ってどういうことか」「私の哲学というものがあるのか―カントの哲学があるように」「哲学史とどうつきあうか」「哲学と科学、芸術、宗教の関係はどうなっているのか」といった問いについて、教員が書いた文章を事前に読み、それに対するレスポンスを(20人前後の)受講生が書いてきて、みんなで披露し合い議論します。本を読み文章を書くことに対するハードルを下げること、そして哲学の勉強が愉しくなることが目標です。
日本美術史

日本美術史の授業風景
日本美術史
担当教員:藤澤 紫
海外でも評価の高い日本の美術、その魅力はいったいどこにあるのでしょう。この講義は、日本の美術や伝統文化に興味を持ち、それらを「見たい・知りたい・楽しみたい!」 と感じる受講生に向けた授業です。「浮世絵とメディア」「アニメーションや漫画の源流」「美術と国際交流」「展覧会の現在」などの身近な観点から、その特質に迫ります。授業の前半はテキストやレジュメを用いた基礎学習、後半はパワーポイント等のビジュアル機器を活用した応用学習になります。簡単な工作も交えて体感的に学びますので、ご一緒に日本美術の豊かな世界を楽しみましょう。
応用倫理学
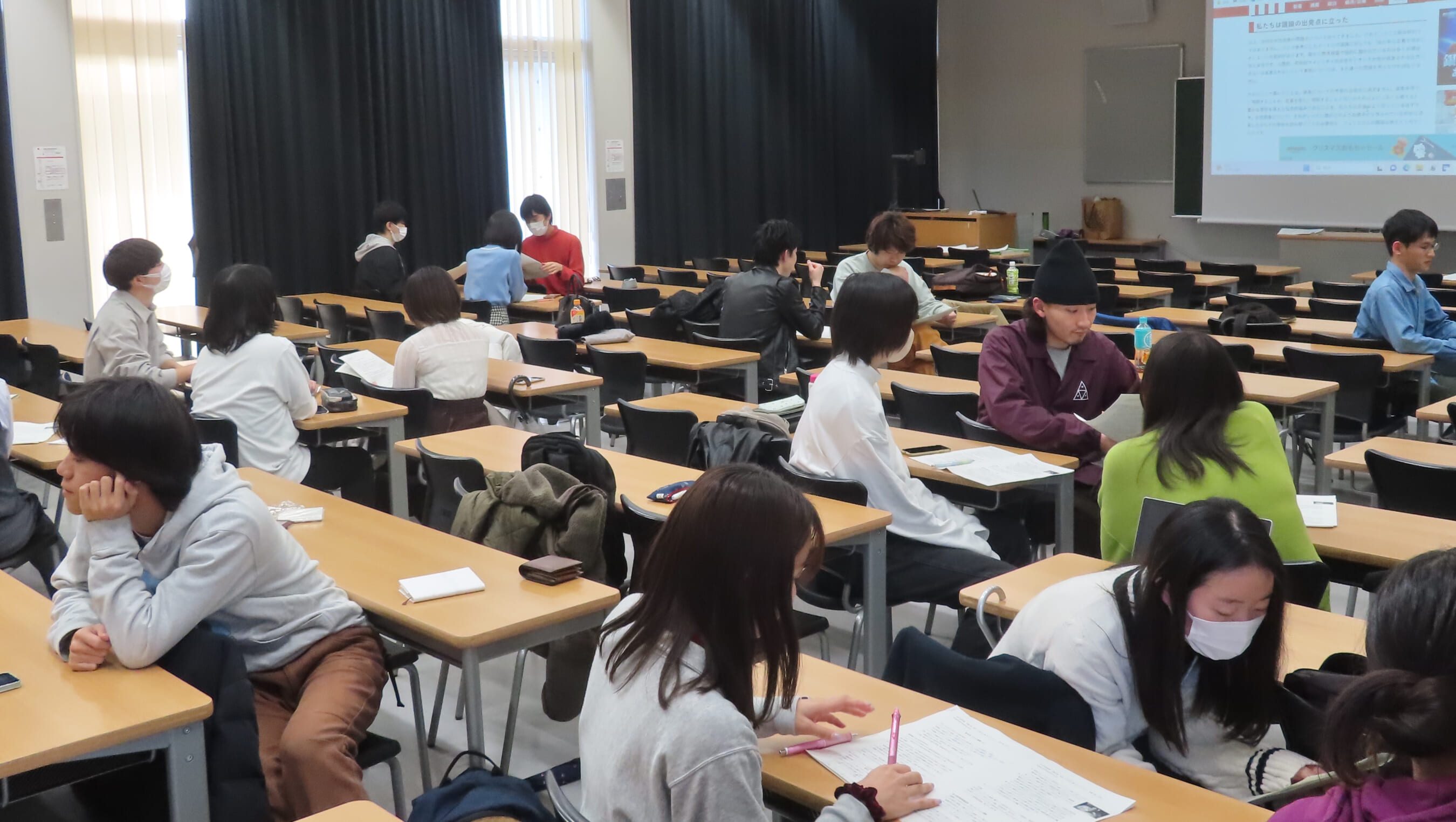
応用倫理学の授業風景
応用倫理学
担当教員:小手川正二郎
国会議員の女性枠を設けることは「逆差別」になるのか、新型出生前診断は障害者を差別することにつながるのか、身体を売り買いすることはどこまで許されるのか、死刑は「最も重い刑罰」と言えるのか、日本は難民をどの程度受け入れるべきなのか。議論の分断や対立に陥りやすいこうした問いをめぐって、応用倫理学の授業では、まず実状についてしっかりと把握したうえで、差別と単なる区別はいかなる点で異なるのか、心身の自由や移動の自由はなぜ、そしてどの程度保障されるべきなのかに遡って考えていきます。そして、グループディスカッションやレポートの相互採点等を通して、異なる立場に立つ人の主張や前提を理解したうえで、受講生一人一人が「自分の頭で考える」ことを試みます。
このページに対するお問い合せ先: 文学部資料室
RECOMMENDS
-
{{settings.title}}
{{settings.lead.title}}
{{{settings.lead.letter}}}
{{pages.title}}
{{articles.title}}
Language
SEARCH
{{section.title}}
-
{{item.tagline}}

